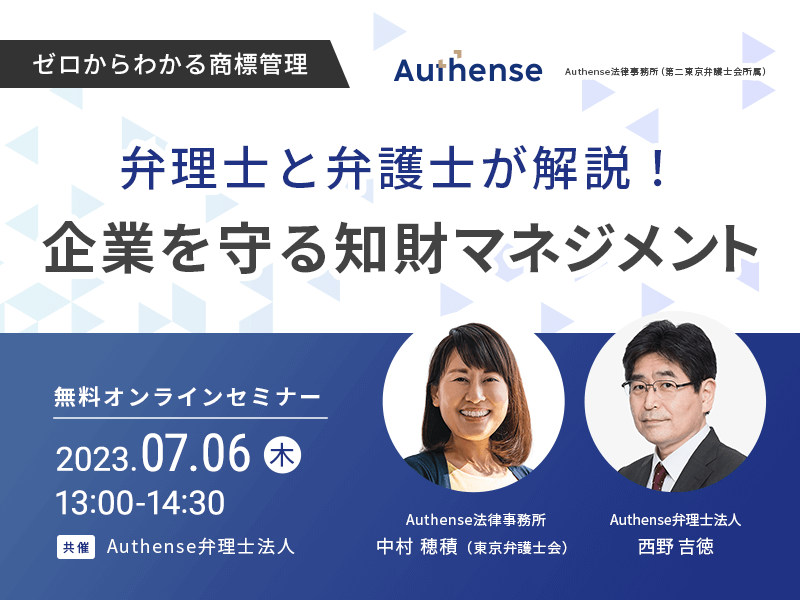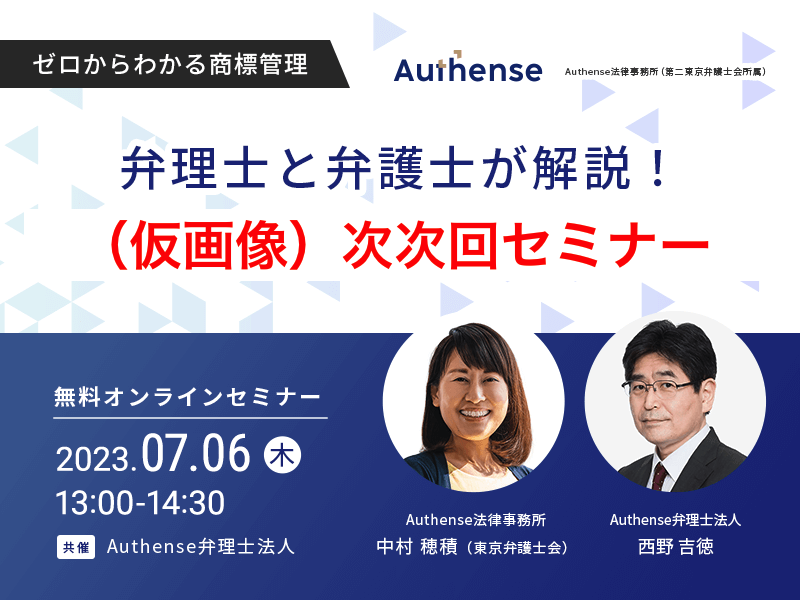えるぼし認定を受けることで「えるぼしマーク」の利用が可能となり、企業イメージの向上につながります。
では、えるぼし認定とはどのような制度なのでしょうか?
また、企業がえるぼし認定を受けることには、どのようなメリットがあるのでしょうか?
今回は、えるぼし認定制度の概要やえるぼし認定を受けるメリット・デメリット、えるぼし認定の申請をする流れなどについて、社会保険労務士(社労士)がくわしく解説します。
なお、当事務所(Authense社会保険労務士法人)はえるぼし認定の申請サポートについて豊富な実績を有しています。
えるぼし認定申請をご希望の際には、Authense社会保険労務士法人までお気軽にご相談ください。
目次
えるぼし認定制度とは
えるぼし認定制度とは、女性の活躍に関する取り組みの実施状況が優良な企業について厚生労働大臣が認定をする制度です。
えるぼし認定を受けるには、女性活躍推進法に基づいて行動計画の策定と届出を行ったうえで、認定申請をしなければなりません。
えるぼし認定申請をご希望の事業者様は、Authense社会保険労務士法人までご相談ください。
えるぼし認定の3段階とプラチナえるぼし認定
えるぼし認定には3段階との認定のほか、プラチナえるぼし認定が存在します。
ここでは、それぞれの概要を解説します。
1段階目
1段階目のえるぼし認定は、後ほど紹介をする「5つの視点」のうち、1つまたは2つの基準を満たした企業に与えられる認定です。※1

1つまたは2つの基準を満たし、その実績を「女性の活躍推進企業データベース」に毎年公表しなければなりません。
また、満たさない項目についても一定の取り組みを実施して2年以上連続して実績が改善していることが要件とされ、その実施状況について公表することが求められます。
2段階目
2段階目のえるぼし認定は、後ほど紹介する「5つの視点」のうち3つまたは4つの基準を満たした企業に与えられる認定です。※1

「女性の活躍推進企業データベース」への公表が必要なことと、満たさない項目の取り扱いについては、1段階目のえるぼし認定と同様です。
3段階目
3段階目のえるぼし認定は、「5つの視点」の基準をすべて満たした企業に与えられる認定です。※1

1段階目や2段階目と同じく、その実績を「⼥性の活躍推進企業データベース」に公表しなければなりません。
プラチナえるぼし認定
プラチナえるぼし認定とは、すでにえるぼし認定を受けた事業主のうち、⼀般事業主⾏動計画の目標達成や⼥性の活躍推進に関する取り組みの実施状況が特に優良であるなどの⼀定の要件を満たした事業者が受けられる認定です。※1

通常のえるぼし認定よりもさらに厳しい8項目の基準をクリアする必要があります。
これからえるぼし認定を申請する際にはまずは通常のえるぼし認定を目指し、その後段階を踏んでプラチナえるぼし認定を目指すとよいでしょう。
企業がえるぼし認定を受ける主なメリット
企業がえるぼし認定を受けることには、どのようなメリットがあるのでしょうか?
ここでは、主なメリットを4つ解説します。
自社のイメージが向上する
えるぼし認定を受けるには、厳しい基準をクリアしなければなりません。
その反面、えるぼし認定を受けることは女性従業員を大切にし、活躍を促進しているという強いメッセージとなります。
これにより自社のイメージが向上し、顧客や投資家などから選ばれやすくなる効果が期待できます。
人材採用で有利となりやすい
えるぼし認定を受けている企業は、女性の活躍推進に重点を置いており、これについて厚生労働大臣から「お墨付き」を得ているといえます。
そのため、求職者から選ばれやすくなり、人材採用において有利となる効果を期待できます。
公共調達で加点を受けられる
公共調達にあたっては入札額の低さのみで落札先が決まるのではなく、企業を総合的に評価する総合評価落札⽅式や企画競争による調達が多く実施されています。
えるぼし認定を受けていることは多くの公共調達で加点の対象とされており、落札の可能性を高めることにつながります。
また、補助金の採択先の審査にあたって、加点対象とされるものも少なくありません。
日本政策金融公庫による融資制度の対象となる
えるぼし認定を受けている場合、低金利である日本政策金融公庫の「働き方改革推進支援資金」の対象となります。※2
ただし、融資にあたっては審査があるため、えるぼし認定を受けたからといって融資が保証されるわけではありません。
えるぼし認定を受けるデメリット・注意点
えるぼし認定を受けることには、デメリットや注意点はあるのでしょうか?
ここでは、主なデメリットと注意点を2つ解説します。
抜本的な体制改善が必要となる可能性がある
えるぼし認定を受けるためにはさまざまな要件を満たさなければならず、これに伴って自社の人事面の仕組みを抜本的に見直す必要が生じる場合があります。
いずれも「えるぼし認定を受けるため」だけに必要となるものではなく、女性の活躍を推進する企業となるために必要な改革ではあるものの、一時的に痛みを伴う可能性があるでしょう。
数値を重視し過ぎて無理が生じるおそれがある
えるぼし認定は認定制度である以上、画一的な数値によって審査せざるを得ません。
そのため、自社の実態に即していないにもかかわらずえるぼし認定への申請を強行的に進めれば、無理が生じて離職者などが出るおそれがあります。
そのため、「えるぼし認定」自体を目的とするのではなく、自社が女性の活躍を推進する企業になることを目指し、その到達度を客観的に確認するものとしてえるぼし認定を目指すとよいでしょう。
自社がえるぼし認定を目指すか否か判断に迷う際には、Authense社会保険労務士法人までご相談ください。
ご相談いただくことで、自社にとってえるぼし認定への申請を目指すことが適切であるか否か判断しやすくなるほか、えるぼし認定を目指すために行うべきことも明確となります。
えるぼし認定を受ける5つの視点
えるぼし認定を受けられるか否かは、5つの項目から審査されます。
ここでは、5つの評価項目についてそれぞれ概要を解説します。
なお、先ほど解説したように、必ずしもすべての項目を満たす必要はありません。
すべての項目を満たした場合には「第3段階」のえるぼし認定の対象となるのに対し、たとえ1つしか満たさない場合であっても「第1段階」のえるぼし認定の対象となります。
自社がどの項目を満たすか確認したい事業者様は、Authense社会保険労務士法人までご相談ください。
採用
1つ目の視点は、「採用」です。
次のいずれかを満たすことで、この基準をクリアできます。
- 男⼥別の採用における競争倍率(応募者数/採用者数)が同程度であること
- 直近の事業年度において、次の両⽅に該当すること
- 1. 正社員に占める⼥性労働者の割合が、産業ごとの平均値(平均値が4割を超える場合は4割)以上であること
- 2. 正社員の基幹的な雇用管理区分における⼥性労働者の割合が、産業ごとの平均値(平均値が4割を超える場合は4割)
継続就業
2つ目の視点は、「継続就業」です。
原則として、直近の事業年度において次のいずれかを満たすことで、この基準をクリアできます。
- 「⼥性労働者の平均継続勤務年数」÷「男性労働者の平均継続勤務年数」が、雇用管理区分ごとにそれぞれ7割以上であること(期間の定めのない労働契約を締結している労働者に限る)
- 「⼥性労働者の継続雇用割合」÷「男性労働者の継続雇用割合」が、雇用管理区分ごとにそれぞれ8割以上であること(新規学卒採用者等として雇い入れた労働者であって、期間の定めのない労働契約を締結している労働者に限る)
ただし、これらの数値を算出ができない場合には、「直近の事業年度において、正社員の⼥性労働者の平均継続勤務年数が産業ごとの平均値以上であること」の要件を満たすことでもよいとされています。
労働時間等の働き方
3つ目の視点は、「労働時間等の働き方」です。
ここでは、雇用管理区分ごとの労働者の法定時間外労働と法定休⽇労働時間の合計時間数の平均が、直近の事業年度の各月ごとにすべて45時間未満であることが求められます。
この要件は、原則として次の式で確認されます。
- 「各月の対象労働者の(法定時間外労働+法定休⽇労働)の総時間数の合計」÷「対象労働者数」 < 45時間
管理職比率
4つ目の視点は、「管理職比率」です。
具体的には、次のどちらかを満たすことが求められます。
- 直近の事業年度において、管理職に占める⼥性労働者の割合が産業ごとの平均値以上であること
- 「直近3事業年度の平均した1つ下位の職階から課⻑級に昇進した⼥性労働者の割合」÷「直近3事業年度の平均した1つ下位の職階から課⻑級に昇進した男性労働者の割合」が、8割以上であること
多様なキャリアコース
5つ目の視点は、多様なキャリアコースです。
具体的には、次の4つの項目について、直近の3事業年度で一定項目を満たした実績が求められます。
- ⼥性の非正社員から正社員への転換(派遣の場合は、雇入れ)
- ⼥性労働者のキャリアアップに資する雇用管理区分間の転換
- 過去に在籍した⼥性の正社員としての再雇用
- おおむね30歳以上の⼥性の正社員としての採用
このうち満たすべき項目は、それぞれ次のとおりです。
- 常時雇用する労働者数が301⼈以上の事業主:2項目以上(非正社員がいる場合は、必ず1を含むこと)
- 常時雇用する労働者数が300⼈以下の事業主:1項目以上
えるぼし認定を受けるための申請方法・流れ
えるぼし認定の申請は、どのような流れで進めればよいのでしょうか?
最後に、えるぼし認定を受けるための申請方法と一般的な流れを解説します。
えるぼし認定にくわしい社労士に相談する
えるぼし認定への申請や、申請のために必要な人事制度の見直しなどを自社だけで行うことは容易ではありません。
そのため、まずはえるぼし認定にくわしい社労士へ相談し、二人三脚で認定を目指すことをおすすめします。
えるぼし認定への申請をご希望の際は、Authense社会保険労務士法人へご相談ください。
実績豊富な社労士が、認定へ向けてサポートします。
一般事業主行動計画を策定し、届け出る
社労士のサポートを受けて一般事業主行動計画を策定し、策定した旨を都道府県労働局へ届け出ます。
的確な一般事業主行動計画を策定するには、策定前に⾃社の⼥性の活躍に関する状況を把握するとともに、課題を分析しなければなりません。
そのうえで、自社が目指すべき方向性を定め、現状との差異を埋めるための行動計画を策定します。
女性の活躍に関する情報を公表する
次に、⾃社の⼥性の活躍に関する状況を公表します。
公表先は「⼥性の活躍推進企業データベース」や、⾃社のホームページなどです。
なお、この公表は常時雇用する労働者数が101⼈以上である事業主には義務である一方で、100⼈以下の事業主へは努⼒義務とされています。
とはいえ、自社が覚悟を持って女性の活躍推進を目指すのであれば、従業員数が100人以下であっても積極的に公表するとよいでしょう。
えるぼし認定申請をする
続いて、えるぼし認定を申請します。
えるぼし認定の申請先は都道府県労働局雇用環境・均等部(室)であり、郵送、持参、電子申請のいずれによっても申請できます。
申請をすると先ほど紹介した視点による審査がなされ、基準をクリアしている数に応じて第1段階から第3段階のえるぼし認定がなされます。
まとめ
えるぼし認定の概要や企業がえるぼし認定を受けるメリット・デメリット、えるぼし認定を受ける基準、申請の流れなどを解説しました。
えるぼし認定とは、女性の活躍に関する取り組みの実施状況が優良な企業を厚生労働大臣が認定する制度です。
認定を受けるには行動計画を策定・届出したうえで、都道府県労働局雇用環境・均等部(室)へ申請しなければなりません。
えるぼし認定を受けることで企業のイメージアップにつながるほか、日本政策金融公庫の融資制度の対象となったり公共調達や補助金で加点されたりするなどのメリットが享受できます。
Authense社会保険労務士法人はえるぼし認定の申請について豊富な実績を有しており、安心してご相談いただけます。
えるぼし認定への申請をご検討の際は、Authense社会保険労務士法人へご相談ください。
お悩み・課題に合わせて最適なプランをご案内致します。お気軽にお問合せください。